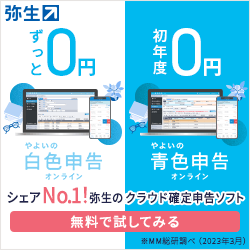弥生会計の「弥生の白色オンライン」は無料クラウド確定申告ソフト 青色帳簿も作成可能な「弥生の青色オンライン」、法人の税務申告も安心の「弥生のクラウド会計・経理・給与」もあります。
弥生会計白色オンラインは無料クラウド確定申告ソフト 青色帳簿も作成可能
弥生会計の「弥生の白色オンライン」は無料クラウド確定申告ソフトです。
そうです! 白色申告なら副業でも個人事業主でもずっと無料で使えるんです。すごいことですよね? 青色帳簿も作成可能な「弥生の青色オンライン」、法人の税務申告も安心の「弥生のクラウド会計・経理・給与」もあります。どちらも無料お試しがあり、複式簿記による帳簿や青色決算書なども作成可能な「弥生の青色オンライン」は、今ならキャンペーン中で、なんと1年間も無料なんです!
弥生レシート取り込みの注意点
弥生レシート取り込みについて解説したのですが、それを使っていく過程で気付いた点が2点あります。それについて解説しています。
レシートは捨てちゃダメ
まず、「この弥生の青色会計オンラインを使っただけでは、レシートをすぐに捨てることはできません」ということです。よく「レシート電子化して保存することができるようになりました」って聞いたことがあります。ただ、その適用を受けるためには、申請書の提出をしたり一定の要件が必要になってきます。 なのでこのアプリを使うだけではレシート電子化することはできません。レシートをすぐに捨てないでください。
スキャンした領収書画像と自動読み取り・入力されたデータを効率よく見比べる
次に、シートの内容を確認する作業の際にこうした方がいいんじゃないかなと思った点があります。 ここのレシートのアイコンをクリックするとこういう画面が出てきます。この状況ではレシートの内容と読み取ったデータがどういう風に合ってるか、どうかっていうこを確認することができません。なので、この画面の配置を、少し変えてみようと思います。 こういう風に左右に並べると、日付や金額が確認しやすいと思います。なので初期設定のままではなくて、こういう風に配置を変えてチェックしていましょう。 ちなみにこの内容、これは経費としては適当だとは思えないので、こういうレシートをアップしないように気をつけましょう。
電子帳簿保存法に対応していないアプリもあるので注意
実は「もうレシートをスマホで撮ればいいんだよね?それだけでいいんだよね?」っていう話になったことがあったんで、ちょっと気になったんで一つ目にその話をしました。「あのアプリを使えばいいんだよね」って思っている方もいると思うんですけど電子帳簿保存法に対応していないアプリもあります。なのでどのアプリが対応しているか確認してから、帳簿の入力を始めるようにしてください。
やよいの青色申告の初期設定について 個人事業主の例
やよいの青色申告のソフトをダウンロードしますとデスクトップ上にアイコンが出てきます。その「やよいの青色申告」のアイコンをクリックしていただくと、こんな画面が立ち上がると思います。
データの新規作成
データの新規作成っていうのがあります。まずここをクリックしていただきますそうすると「新規にデータを作成する」と出てきますので、一番上にチェックをして、「個人一般」を選んでください。事業主様の名前とその住所、屋号を入れていただくということです。 次に、会計年度を入力します。個人事業主の場合は必ず暦年の1月1日からとなります。「電子帳簿の保存をおこなわない」ことにしてください。税務署に届け出が必要だからです。コンピューターに保存してください。 消費税なんですけれども、免税や課税は人によって違いますが、今回の説明は免税でおこなっていきましょう。これで初期設定は終わりです。
個人事業主さんのための帳簿の付け方について
青色申告の帳簿の付け方、仕訳帳をマスターしようということなんですけど、今たくさんの会計ソフトが出ていまして、どれもいろんな機能が付いていてとても便利になっているかと思います。今回みなさんに会計ソフトの入力手順をご説明しようと思って、実際に色々な会計ソフトを見てみたんですけど、前は会計ソフトって現金を使ったら現金出納帳、銀行の預金のお金を使った取引だったら預金出納帳に入力するというように、各取引によって帳簿を分けて入力していたんですけど、今は簡単入力みたいな機能があって、それを使えば自動的にいろんな帳簿を勝手に会計ソフト内で自動作成してくれるようになっているんですね。
各帳簿を勝手に会計ソフト内で自動作成してくれるので簡単
この今言った「簡単入力」みたいなものを見てみたんですけど、これがですね意外と簡単なので、ちょっと実際に見てみたいと思います。これ弥生会計のクラウド確定申告ソフトなんですけど、ここに簡単入力ってありますよね。これ実際見て、ここから項目を1個ずつ選んで入力していくんですけど、意外と「収入から選ぶか支出から選ぶ」とか、この選ぶのが意外と面倒くさいんじゃないかなと思いまして何かいい方法はないかなーって思ったんですけどちょっと戻りますね。それが8個です。会計ソフトはたくさんあるけれど仕訳帳なら入力方法 と一つということです。
仕訳帳は青色申告をするために必ず必要な帳簿
この仕訳帳っていうのは青色申告をするために必ず必要な帳簿なので、個人事業主の方みんなが必要な帳簿になります。この仕訳帳っていうの、は基本となる帳簿なのでこれはどの会計ソフトにもあって、入力方法はどれも全部一緒ですなので、この仕訳帳の入力さえマスターしてしまえば、どんな会計ソフトでも使いこなせることができるようになるわけなんですね。 この仕訳帳の入力さえできれば、仕訳帳っていうそのもの自体は会計ソフトが自動作成してくれますので、難しいことは考えずにこの仕訳帳の入力だけを覚えれば大丈夫です。なので今日はここで一緒にこの仕訳帳の入力方法を見ていきたいと思います。
複式帳簿=右と左が同じ金額になるように入力する
では一つ目、右と左が同じ金額になるように入力するということなんですけど、これはどういうことかって言うとですね、実際に見てみましょう。ここで仕訳帳入力っていうの選びますよ。これ仕訳帳の入力する一行ぶんになるんですけど、右と左が同じ金額になるように入力するっていうのは、ここのここに金額が二つあるんですね。複式簿記っていうのは、この部分で右と左に分けるものなんですね。項目が右ですか左ですかというのが重要で、この右の金額と左の金額が一緒になるように同じ金額を入力してくださいっていうのが今の話です。
現金で支払った場合の入力例
先ほどの方に戻る、例えば現金にしますけど、
ってことなんですけ、ど現金を使った時いうのが自分のお金が減っていく時なので、こっちに勘定科目に例えば入れて頂いて、1000円なら1000円って入力します。こっち、例えば携帯のお金とかで通信費だとしたら、「通信費」で、そんな感じで右の1000円と左の1000円、これで右に金額一緒ですね、右と左で使ったバージョンなので、右側に金額。これ反対に例えば売上とかでお金が入ってきた場合は、こっちにお金現金が現金で入ってくることはあまりないかもしれないですけど、こっちが現金になりますね。 でまた戻ります。この右と左が同じ金額になるようにする。「使った時が右に現金、入ってきた時が左に現金」 まずはこの二つを覚えてください。
- 日付
- 勘定科目
- 金額
- 摘要
を入力する。
勘定科目
勘定科目っていうのはお金の内容を示したものですね。文房具を買いました。その「文房具」って入力するわけじゃなくて、
- 文房具って消耗品費、
- 携帯代を払ったとしたら携帯代は通信費、
- 取引先とのお食事した場合は交際費、
- お仕事に関係する本を買った場合とかは新聞図書費
だったりこういう風に決まった項目があるので、それを勘定科目と言います。
摘要は取引の内容を示したもの
摘要ですね。摘要というのは取引の内容を示したものです。領収書の「但し書き」ですね。例えば「何々代として」ありますよね。あれですね。「どこで、いつ、何に、お金を使ったか」が分かるようにするのがこの摘要になります。 伝票を入力する時、この、日付・勘定科目・金額・摘要を必ずチェックしてください。入力する時は必ず領収書や請求書を見ながら入力するのは基本です。領収書が手元にない状態で入力してしまうと、後から二重の入力になってしまうこともあるので、必ず領収書を見ながら入力するようにしてください。 たぶん疑問に皆さんが帳簿をつけながら思うのはこの勘定科目だと思うんですけど、「勘定科目の選び方」はまた別に詳しくやりますので、今日はとりあえず「日付・勘定科目・金額・摘要、この四つを入力するのが基本」っていうことだけ覚えてください。
実際に仕訳帳に入力してみよう
例えば4月1日業務で使う文房具1000円を現金で購入した場合。 先ほどの入力ために戻ります。先ほど「日付・金額・勘定科目・摘要を入力しましょうと説明しました。日付は4月1日でしたよね。ですから文房具なので消耗品費。 補助科目というのは気にしなくて大丈夫です。「現金でA商店」。現金ですよね A商店で文房具代としてということになります。これが摘要。現金を使った場合なので、右に現金が来てますよね。これでこの帳簿は「消耗品(文房具)に対して1000円の現金を出しましたよ」っていう帳簿の付け方で、摘要が、ここにどこどこで何に使ったかを書いてください。日付とかはここにあるので特に書かなくても大丈夫です。以上が基本となる仕訳帳の入力で、今日行ったところがわかると、基本的には経費の仕訳帳の入力ができるようになります。 現金払いにする場合は、必ず右に現金。入ってきた時は左に現金が来ることになります。日付・勘定科目・金額・摘要をきちんと入力してください。勘定科目はまた別でやります。摘要には取引の内容、どこで何に使ったかですね、を記入するようにしてください。「もしこの勘定科目はどういう時に使うんですか」とか「この領収書の勘定科目は何になりますか」っていう分からない所があったら、税理士ドットコムで質問するのがオススメです。